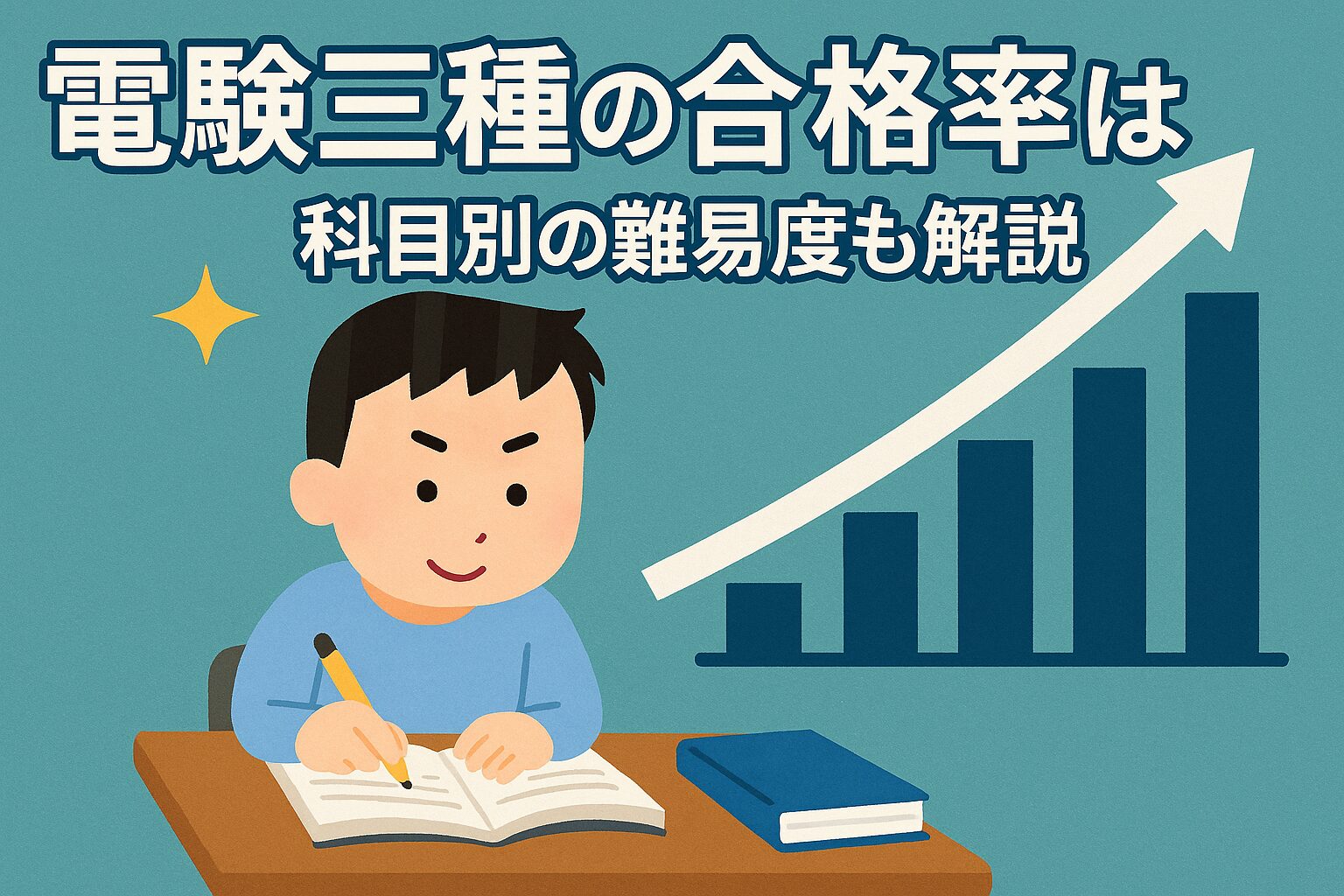【はじめに】
「電験三種って難しいって聞くけど、実際の合格率は?」「どの科目が一番むずかしいの?」
この記事では、電験三種の全体的な合格率から、科目ごとの難易度や出題傾向、 そして初学者がよくつまずくポイントまで、詳しく丁寧に解説していきます。
初めてこの資格に挑戦する方でも、自分の現在地を把握し、適切な学習戦略を立てられるようになることを目指しています。
【電験三種の全体合格率】
電験三種は「理論」「電力」「機械」「法規」の4科目に合格することで取得できる国家資格です。
過去10年の平均合格率は約8〜12%。 受験者数は年間4〜5万人で、合格者数は約4,000〜5,000人前後です。
▼ 年度別合格率の一例(平均値)
- 2020年:約9.3%
- 2021年:約8.5%
- 2022年:約12.2%(CBT方式導入年)
CBT方式が導入されたことにより、試験の環境が柔軟になったため、受験者にとっては若干有利になっている印象です。
また、2022年からは年1回だった試験が年2回(上期・下期)に拡大され、受験のチャンスが増えています。
この背景には、電験三種の有資格者が高齢化し、電気保安人材が不足しているという構造的な課題があるとされています。
「このままでは現場が回らなくなる」との声もあり、国全体として“合格者を増やす必要性”が高まっているのです。なので難易度が下がっている今がチャンスなのです。
【科目別の合格率と難易度】
各科目はそれぞれ傾向が異なり、得意・不得意も分かれます。以下の順番で取得する人が多いです。
🔹 理論(最初の壁・計算がメイン)
- 合格率:約15〜25%
- 内容:電気回路、オームの法則、ベクトル、コンデンサ、交流回路など
- 特徴:基礎が問われるが計算問題が多く、数学が苦手な人にはハードルが高い
💡ドラクエで例えるなら、「最初の村を出た後のはじめてのボス戦」 基礎ができていないと、いきなり全滅します。
🔹 電力(暗記+計算のバランス型)
- 合格率:約20%前後
- 内容:送電・配電・変電・高圧設備・発電方式など
- 特徴:内容は幅広いが、出題傾向が安定していて対策しやすい
💡ドラクエで言えば「中盤のフィールド」 敵は強いが、事前に装備(暗記)を整えれば何とかなるゾーン。
🔹 機械(最大の鬼門)
- 合格率:約10〜15%
- 内容:電動機、変圧器、パワエレ、照明、情報処理など
- 特徴:分野が広く、一部は“理論”より難しい計算も登場
💡ドラクエで言えば「終盤の大型ダンジョン」 覚えることが多く、どこから手をつけていいかわからず迷子になり心が折れる人続出。
🔹 法規(得点源にもなる暗記科目)
- 合格率:約25〜30%(最も高い)
- 内容:電気事業法、電技解釈、施設管理、安全基準など
- 特徴:暗記中心。計算問題も一部あり。
💡 ドラクエで例えようと思ったが、こいつは別ゲーです。マリオです。必要な能力が違います。
対策すれば一番点を稼ぎやすいが、油断すると“見落としミス”で取りこぼす。実は法規だけ合格せずに電験三種を諦めるパターンが多い(詳しくは別記事で解説します)
【科目合格制度とは?】
電験三種には「科目合格制度」があります。 これは、1回の試験で4科目すべてに合格しなくても、合格した科目は3年間有効になるというもの。
たとえば、
- 2025年に「理論」と「法規」に合格
- 2026年と2027年の試験で残り2科目に挑戦
という戦略も可能です。
社会人や忙しい人でも、自分のペースで取得を目指せる柔軟な制度となっています。
【独学者がつまずきやすいポイント】
- 理論と機械を同時にやるとパンクする:どちらも計算と理解を要するため、初学者は順番にやるのが◎
- 機械の範囲が広すぎてモチベが保てない:まずは「変圧器」「直流電動機」から集中
- 法規を軽視して後悔:点が取りやすいからこそ、取りこぼすと致命的
学習の順番、過去問の活用法、インプットとアウトプットのバランスが成功のカギです。
【まとめ】
電験三種の合格率は決して高くはありませんが、 「合格者は1万人に満たない」という点こそが“価値”の証明でもあります。
ドラクエのように、最初はスライムにも負けるかもしれません。 でも、一歩ずつレベルを上げ、武器(知識)と防具(計算力)をそろえていけば、 必ずラスボス(合格)を倒せる日がきます。
まずは自分の得意・不得意を見極め、戦略的に1科目ずつクリアしていきましょう。
あなたの電験三種合格の冒険、ここから始まります。