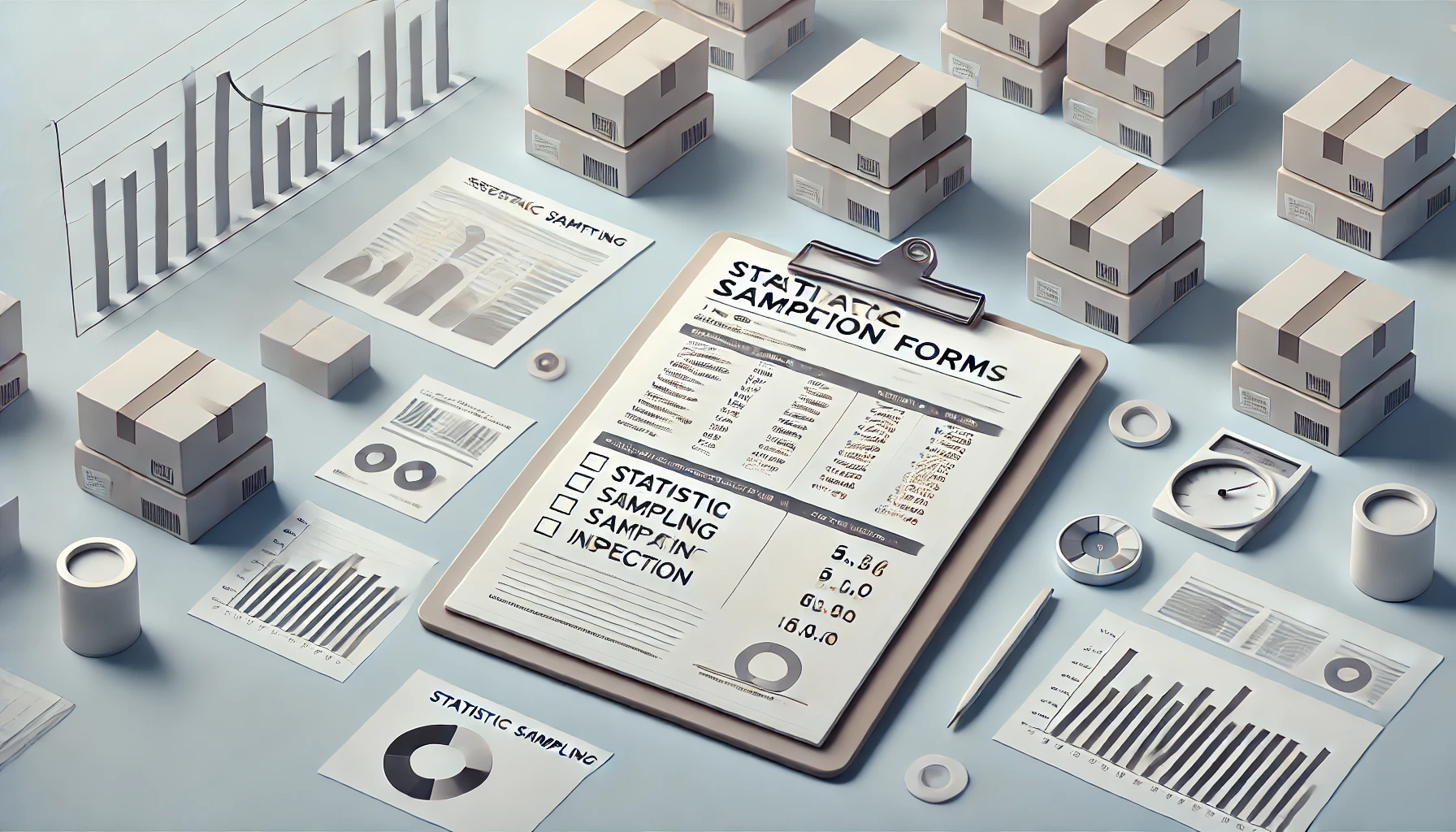目次
検査の「形式」とは?
抜取検査において「何回抜き取るか?」「判定をどう進めるか?」という実施方法の違いを分類したものです。
抜取検査の主な4形式
| 形式 | 説明 | 特徴 |
|---|---|---|
| ① 一回抜取検査 | 1回だけサンプルを抜き取って合否判定 | 最もシンプルで基本的な方法 |
| ② 二回抜取検査 | 1回目の検査で判定がつかない場合、2回目を実施 | 統計的に効率が良い |
| ③ 多回抜取検査 | 判定がつくまで複数回抜取検査を行う | 調整可能だが管理がやや複雑 |
| ④ 逐次抜取検査 | サンプルを1個ずつ取り、1個ごとに判定を更新していく | 合否判定が最も早くつく可能性があるが、設計が難しい |
① 一回抜取検査(Single Sampling Plan)
✔ 特徴:
- 一度だけ抜取(例:n = 80)、不良が c 個以下なら合格
- 最もシンプル、実務でも広く使われる
✔ メリット:
- 管理・運用が簡単
- 検査が早く終わる
✔ デメリット:
- サンプル数が多くなりやすい
- 合否判定の柔軟性がない(1回勝負)
② 二回抜取検査(Double Sampling Plan)
✔ 特徴:
- 1回目で不良が少なければ合格、多ければ不合格、中間なら2回目検査
- 例:1回目 n₁ = 50、c₁ = 1、r₁ = 4 → 2回目 n₂ = 30
✔ メリット:
- 平均検査量が抑えられる(判定が早くつけば2回目不要)
- 精度と効率のバランスが良い
✔ デメリット:
- 手順がやや複雑(表の読み方に注意)
③ 多回抜取検査(Multiple Sampling Plan)
✔ 特徴:
- 3回以上の抜取を前提にした検査設計
- 判定が「合格でも不合格でもない」状態が続くと、さらに検査が進む
✔ メリット:
- 判定精度が高まる
- 品質に関する微妙な判断ができる
✔ デメリット:
- 管理が複雑(都度判定のルールが必要)
- 実務ではあまり使われないことも多い
④ 逐次抜取検査(Sequential Sampling Plan)
✔ 特徴:
- サンプルを1個ずつ抜き取り、その都度判定
- 「合格 or 不合格 or 続行」の3つのゾーンを持つ
✔ メリット:
- 平均的な抜取数が最も小さくなる
- 判定までのスピードが非常に速い
✔ デメリット:
- 検査計画と判定ラインの設計が難しい
- 運用が煩雑
判定フローのイメージ(比較)
| 形式 | 判定ステップ |
|---|---|
| 一回抜取検査 | 検査 → 判定(1回で完了) |
| 二回抜取検査 | 検査① → 判定① → あいまいなら検査② → 判定② |
| 多回抜取検査 | 判定がつくまで繰り返し |
| 逐次抜取検査 | 1個ずつ → 都度判定・グラフで判断 |
まとめ:形式と型の違いを区別しよう
| 観点 | 「型」 | 「形式」 |
|---|---|---|
| 意味 | ロットの扱い方(規準型・選別型・調整型) | 検査の進め方(何回?どう判定?) |
| 判断軸 | 不合格ロットをどうするか | 検査回数と判定タイミング |