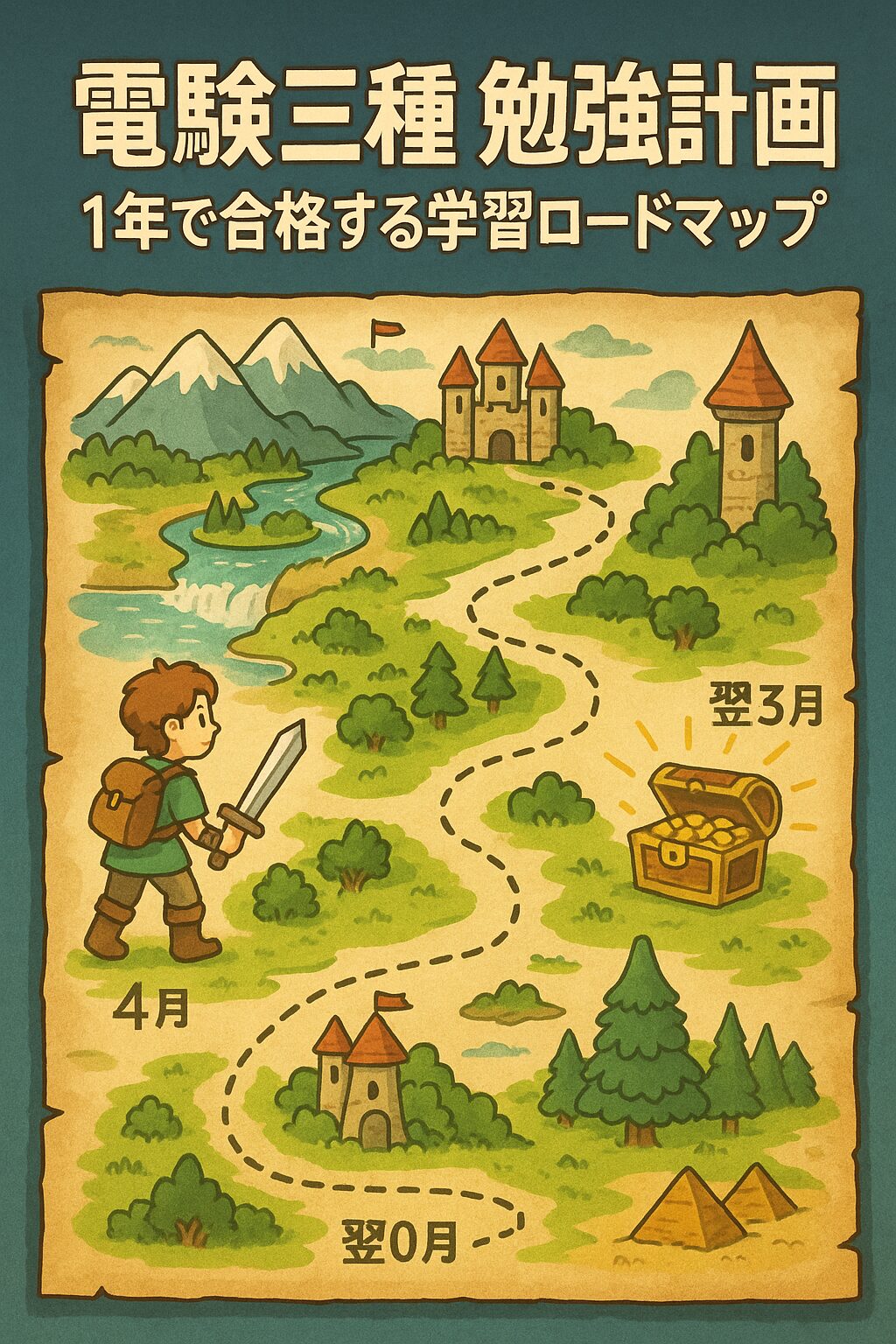目次
1. はじめに|1年で電験三種に合格するために
「電験三種って、1年で合格できるの?」 ──結論から言えば、本気で勉強を習慣化できれば、実は可能です。
電験三種は難関国家資格として知られています。 合格率は全体で10%前後、4科目すべてに合格する必要があり、出題範囲も非常に広い。
でも、実際に合格した多くの人が口を揃えて言うのは── 「内容そのものよりも、継続することが一番難しい」ということ。
つまり逆に言えば、「毎日少しずつでもやり続けられる人」なら、 電験三種は誰でも狙える資格なのです。
このブログでは、学習法だけでなく、モチベーション維持に役立つ記事も発信しています。 「仕事が忙しい」「今日は疲れた」「勉強のやる気が出ない」──そんな悩みにも、具体的な対処法を紹介してきました。
今回は、その集大成ともいえる記事として、 1年で電験三種に合格するための決定版学習ロードマップをお届けします。
勉強計画を立てる前に、やらなくていい勉強を知っておくことも重要です。電験三種 合格者が語る「やらなくてよかった勉強」ワースト5で無駄を省きましょう。
2. 電験三種の試験スケジュールと科目合格制度の活用
電験三種は現在、年2回(上期8月・下期3月)受験できる国家資格です。 CBT方式の導入により、自分のスケジュールに合わせた受験がしやすくなりました。
さらに、1度合格した科目は3年間有効な「科目合格制度」があるため、 1年で全科目に合格しなくても、部分的に積み上げていくことができるのです。
「4科目一発合格を目指す」のではなく、 「上期で得意科目を確実に取り、下期で苦手を潰す」という 戦略的な2段構えが合格への近道です。
3. 勉強開始前にやるべき準備
勉強を始める前に、以下の準備をしておきましょう:
- 年間スケジュールを把握(試験日・申込期間)
- 教材選定:入門書・演習本・過去問セットを用意
- 学習スタイルの選定(朝活型・通勤型・夜集中型など)
- 学習記録ノートやアプリを使って“見える化”
また、SNSやこのブログを活用して仲間を見つけたり、励まし合える環境を作っておくと、継続の支えになります。
帰宅後の勉強習慣化には、電験三種|帰宅後5秒で勉強モードに入る"トリガー仕組み"の作り方が効果的です。
4. 年間スケジュール(上期+下期の2回受験)
| 月 | フェーズ | 内容 |
|---|---|---|
| 4月 | 準備 | 試験スケジュール確認・教材準備 |
| 5〜6月 | インプット① | 理論+電力の基礎固め |
| 7月 | 演習① | 理論・電力の過去問演習+模試対策 |
| 8月 | 上期受験 | 理論・電力を受験(+機械or法規) |
| 9月 | 分析 | 結果を見て戦略調整・モチベ維持策も導入 |
| 10〜11月 | インプット② | 機械・法規の理解と反復 |
| 12〜1月 | 演習② | 全体の復習+弱点強化 |
| 2月 | 仕上げ | 模擬試験・法規暗記・確認テスト |
| 3月 | 下期受験 | 残りの科目を受験→合格完成! |
📅 4月:準備月(戦略を立てて、道具を揃える)
-
✅ 目標:全体像を把握し、学習を「習慣化」する環境を整える
-
✅ 内容:
-
試験日程・申込スケジュール(CBT予約も)を確認
-
教材選び(入門書・問題集・過去問)を完了させる
-
スケジュール帳や学習管理アプリを導入
-
-
✅ 注意:
-
ここで学習ペースが決まる。無理に始めるより「続けられる時間」を試して慣れる
-
SNS・ブログなど“学習仲間”のいるコミュニティに参加するのも◎
-
📅 5月:理論の基礎固め① +電力スタート
-
✅ 目標:理論を中心に週15〜20時間を確保
-
✅ 内容:
-
理論の公式(オームの法則・電力・ベクトル・交流)をインプット
-
電力は送電・発電・配電の全体像をざっくり掴む
-
-
✅ 注意:
-
計算問題が中心。手を動かして「慣れる」ことが大事
-
苦手意識が芽生えたら動画教材で“イメージ”から入るのもアリ
-
📅 6月:理論・電力の中級演習期
-
✅ 目標:過去問の理論で6割、電力で5割程度の得点力をつける
-
✅ 内容:
-
理論は過去問の「基礎問題」から着手
-
電力は高圧設備・変電所系の出題にも触れる
-
1週間に1度は「まとめノート」や振り返りを
-
-
✅ 注意:
-
まだ完璧でなくてOK、理解度7割くらいを目指す
-
勉強が“作業”にならないよう、たまにアウトプットすること
-
📅 7月:実戦演習&上期試験対策
-
✅ 目標:過去問の理論・電力で8割解ける状態を作る
-
✅ 内容:
-
時間を測って解く模試形式の問題に挑戦
-
苦手単元を潰し、法規・機械は少し“つまみ食い”しておく
-
CBT方式での出題形式にも慣れておく(例:パソコンで解く練習)
-
-
✅ 注意:
-
メンタルに波が出やすい時期。睡眠・食事・運動も大事に
-
直前1週間で「できることを増やす」より「できないところを減らす」
-
📅 8月:上期試験本番(理論+電力+α)
-
✅ 目標:少なくとも理論+電力で2科目合格
-
✅ 内容:
-
可能なら法規or機械も一緒に受験(経験値アップ)
-
試験直後は復習メモを残しておくと、次回受験時に役立つ
-
-
✅ 注意:
-
試験後に「疲れて燃え尽きる」パターンが多い。気を抜きすぎないこと
-
📅 9月:仕切り直し&学習計画の再構築
-
✅ 目標:上期結果を分析し、下期戦略に切り替える
-
✅ 内容:
-
合格した科目は週1復習ペースへ
-
機械・法規を新たにスタート。苦手意識をなくす時期
-
-
✅ 注意:
-
モチベーションが落ちやすい。やる気が出ない日は“5分だけ”でも教材を開こう
-
📅 10月:機械の基礎 + 法規の全体像把握
-
✅ 目標:機械の出題範囲に慣れる(変圧器・電動機・照明など)
-
✅ 内容:
-
法規は暗記が中心。条文ベースではなく「ストーリー」で覚える
-
計算問題も含めて、週に1日は理論・電力の軽い復習も継続
-
-
✅ 注意:
-
機械は範囲が膨大なので「優先順位」が重要(重要単元から)
-
📅 11月:応用問題演習 + 法規暗記スタート
-
✅ 目標:過去問で得点力を積み重ねる
-
✅ 内容:
-
法規は「過去に出た数値・文言・単語」の暗記カードを作ると効果的
-
機械は3〜4単元に絞って反復
-
-
✅ 注意:
-
「やったつもり勉強」にならないように、解けなかった問題は翌週リトライ
-
📅 12月〜1月:実戦モード突入(全科目対応)
-
✅ 目標:試験形式で全科目を解けるようにする
-
✅ 内容:
-
模擬試験(2時間×4科目)のシミュレーション
-
タイムマネジメント(時間配分/マークミス防止)
-
-
✅ 注意:
-
完璧は目指さない。60〜70点の再現性を重視
-
焦りが出てくる時期なので、メンタルケアも忘れずに
-
📅 2月:総仕上げ + 弱点潰し
-
✅ 目標:残り1ヶ月で“あと10点伸ばす”工夫をする
-
✅ 内容:
-
苦手箇所を「ピンポイントで解く」練習
-
法規の数字・条文暗記は朝イチにやると定着しやすい
-
-
✅ 注意:
-
無理に新しいことはやらず、「やってきたことを信じる」ことが大切
-
📅 3月:下期試験本番(残りの科目)
-
✅ 目標:ここで全体合格を完成させる
-
✅ 内容:
-
前日は“軽めの復習”で気持ちを整える
-
当日は「自分の得意科目から」解いてリズムをつくる
-
-
✅ 注意:
-
CBT特有の操作ミスに注意(マーク漏れ・見直し忘れ)
-
5. フェーズ別の学習戦略と重点ポイント
電験三種における「継続的なフェーズごとの学習戦略」だけでなく、科目ごとに押さえるべき重要ポイントを明確にすることで、学習効率は飛躍的に高まります。 以下に、理論・電力・機械・法規の4科目それぞれについて、試験対策として押さえておくべき戦略・ポイント・注意点を詳しく解説します。
🧪 理論(電気理論)
- 最初に取り組むべき科目。全体の土台であり、電力・機械の理解にも直結。
- 計算問題が中心で、公式を覚えるだけでなく“使える”ようになることが必須。
対策ポイント:
- 直流回路・交流回路・ベクトル演算の理解は最優先。
- 苦手な人は図解が豊富な参考書を使って「イメージ→数式」の順で学習。
- 毎日少しでも計算問題に触れ、“感覚”を保つ。
- 理論は「応用よりも基礎の徹底」で点が取れる。
- 過去問演習では、公式を見ずにスラスラ解ける状態まで繰り返す。
- 基本公式(オームの法則、合成抵抗、電力量、力率)を、言葉でも説明できるように。
⚡ 電力(電気エネルギーの供給と制御)
- 理論と並行して学ぶことが多い。内容は広く浅い印象。
- 覚える量は多いが、出題傾向が安定している。
対策ポイント:
- 発電(火力・水力・原子力)→送電→配電→受電設備の“流れ”をつかむ。
- 出題頻度が高いのは、三相交流・変圧器・電力損失・地絡など。
- 数値や条件(電圧、周波数、損失率など)を図で整理すると記憶しやすい。
- 電線の太さや材質ごとの特性(銅とアルミなど)を表で比較しておく。
- 暗記で取れる問題も多いため、“捨て問”を見極めて60点確保を狙う。
- 試験前は「一問一答形式」で瞬発力を鍛えると得点効率アップ。
⚙️ 機械(電気機器・電子回路・自動制御)
- 出題範囲が最も広く、文系出身者や独学者がつまずきやすい科目。
- 計算問題・構造理解・暗記が混在し、「総合力」が問われる。
対策ポイント:
- 優先順位をつけて攻略:「変圧器」「誘導電動機」「直流機」「同期機」→次に照明・制御系。
- 一度で理解しにくいテーマは、YouTubeや図解書で視覚情報を活用。
- 回路図記号や構造の名前だけでも覚えておくと、選択問題で有利。
- 誘導電動機の回転原理や同期速度、効率計算などは出題率が高い。
- 自動制御の単元(制御量、フィードバックなど)は早めに手をつける。
- 過去問では“間違える分野”を3回繰り返す→苦手潰しが合格への鍵。
📜 法規(電気法令・電気設備の基準)
- 暗記が中心だが、「覚えるだけでは点が取れない」と感じる人も多い。
- 点が取りやすい一方で、試験直前の詰め込み型だとミスが出やすい。
対策ポイント:
- 「高圧受電設備の設置基準」「感電防止対策」「保安規定」などの出題が多い。
- 過去問の条文やキーワード(設置距離、定格電圧、地絡保護)を抽出して“数字カード”を作る。
- 時間をかけるより“回数をこなす”ことで定着しやすい。
- 公式(電力=VIcosθなど)も出るため、理論とのリンク意識を忘れずに。
- 1日10分×3回などの“細切れ暗記”が最も効果的。
- 模試や演習問題では「なぜこの条文が正解か?」まで確認する。
このように、各科目には「学ぶ順序」や「向き合い方」によって、大きく学習効率が変わるポイントが存在します。単に問題集を解くだけでなく、自分なりの戦略で攻略する意識を持つことが、電験三種合格への近道となります。
6. 上期・下期それぞれの受験戦略
上期(8月)では、理論と電力を中心に2〜3科目受験。 まずは「取れるところから確実に取る」ことを意識。
下期(3月)では、上期で漏れた科目+機械・法規に集中。 試験直前期に「覚えるだけで取れる法規」で点数を底上げする。
7. 習慣化できれば実は誰でも狙える
繰り返しになりますが、電験三種で最も難しいのは“内容”ではなく、 継続して勉強することそのものです。
- やる気が出ない日でも、最低5分だけでも机に向かう
- 1日30分だけでも“継続する自分”をつくる
- スマホ時間を1/3減らすだけで1日60分勉強に変えられる
習慣化できれば、誰にでも合格の可能性がある資格です。 勉強が“歯磨きのように当たり前”になれば、もう怖くありません。
忙しい社会人の方は、電験三種 スキマ時間勉強術|通勤30分を得点に変える方法も活用してください。
8. このブログではモチベ維持の記事も発信中
このブログでは、勉強法の紹介だけではなく、 「やる気が出ないとき」「何から始めればいいかわからない」 といった方向けに、モチベーション維持に関する記事や体験談も発信しています。
- 合格者の1日スケジュール
- 仕事と勉強の両立術
- 勉強に集中できる朝活のすすめ
- サウナや筋トレとの併用でリフレッシュする方法
読者の皆さんの実生活に寄り添いながら、 “電験三種に本気で挑むあなた”を後押しする内容を届けていきます。
9. まとめ|試験に“勝つ”には戦略がいる
電験三種を1年で合格することは、決して夢ではありません。
ただし、それには「やみくもに勉強する」だけでは不十分です。
- 明確な戦略(科目ごとの優先順位)
- 現実的なスケジュール(年2回受験)
- 継続できる学習習慣(30分でもいいから毎日)
この3つを持って、初めて「電験三種に勝てる人」になります。
自分の未来を変えるのは、今の選択。 今日から少しずつ、合格への一歩を積み上げていきましょう。