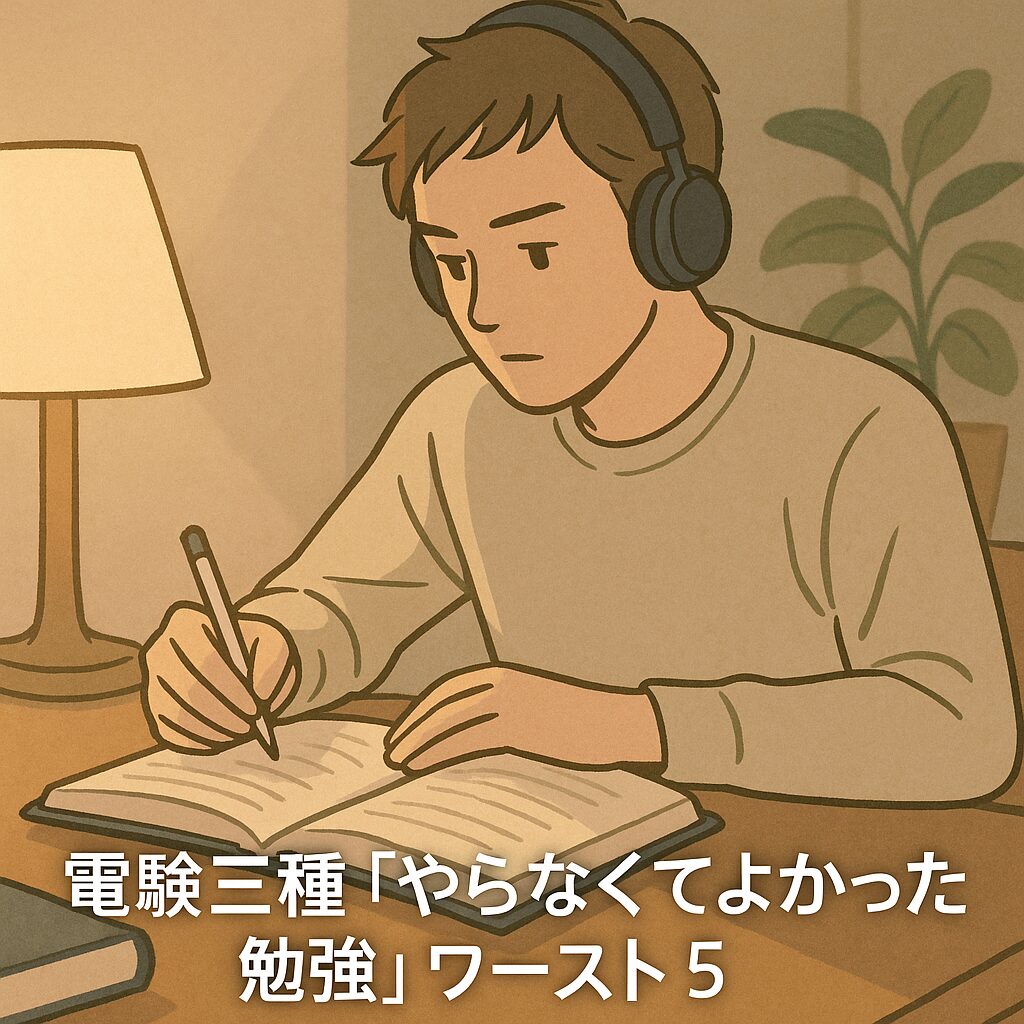目次
はじめに|「努力の方向」を間違えると、合格はいつまでも遠い
電験三種の勉強を始めると、多くの人が「何をやれば点が取れるか」を探します。
しかし本当に差を生むのは、“何をやらないか” を先に決めた人です。
たとえば、地図にない寄り道で体力を削られたり、レベル上げに不要なモンスターと戦い続けたり──。
ドラクエの世界なら「その行動はムダだ」とすぐ分かりますが、試験勉強になると不安からつい遠回りを選びがち。
そこで本記事では、合格者が声を揃えて「やらなくてよかった」と断言した失敗パターンをワースト5形式で公開。
‐ なぜムダになるのか
‐ 代わりに何をすべきか
を具体的に示します。
ムダを斬り、得点源だけを残す――それが最短合格ルート。
読み終えたとき、あなたの学習計画はきっと身軽になり、ゴールまでの距離がぐっと縮まるはずです。
“やらないこと”を決めてから勉強を始めると、総学習時間が2~3割減でも合格点に届きます
逆に「やるべき勉強」を体系的に知りたい方は、電験三種 勉強計画|1年で合格する学習ロードマップをご覧ください。
https://shirasusolo.net/dennkenn/learning-strategy/post-1254/
5 位 古すぎる年度過去問を やる
ありがちな失敗
-
2000 年以前の問題までさかのぼって「量=正義」と信じて解きまくる
- 会社や学校から借りた過去問題集が古かったがそのまま解きまくった。
なぜムダか
-
出題形式・単位系・数値トレンドが現在とズレており得点期待値が低い
-
25 年分解くなら 250 時間以上、直近 10 年×3周のほうがコスパ大
合格者の代替案
-
直近 10 年 を 分野別(理論→電力→機械→法規) に並べ替えて3周
-
「CBT 導入後(2022~)」は 別フォルダ で重点演習
4 位 法規条文を全文書き写す“写経”勉強
ありがちな失敗
-
気合いで条文をノートに丸写し→満足して読み返さない
なぜムダか
-
電験三種の法規は “数字とキーワード”で点が取れる
-
条文丸写しは 時間単価が極端に悪い(60 分写して 0 点のリスク)
合格者の代替案
-
必要なのは 「数字・固有名詞・例外条件」 だけ
-
で 数字カード 100 枚 を作り、スキマ時間に反復
-
条文全文を確認するのは カードで覚えた数値が本当に合っているか検証するときだけ
3 位 公式を暗記してから問題演習に進む“順序固定”
ありがちな失敗
-
「覚えてからでないと不安」と公式集を丸暗記 → 数日で忘却 or 用途がわからず戸惑う
- 公式の意味や成り立ちに意識が向きすぎて、学習が全然進まない。
なぜムダか
-
電験三種の公式は “使い方”を問題で体感 しないと定着しない
-
暗記直後は覚えた気になるが 演習で再現できない → 二度手間
→まずは問題演習で公式を使って見るのが最優先
合格者の代替案
-
問題先行 → 公式確認 → 再演習 の“3ステップ回転”
-
1問解いたら解説を読み、公式をカードに追加して次の周回で再利用
-
公式暗記と演習を1セットにすると 学習効率が 1.5~2 倍 に跳ね上がる
2 位 参考書&問題集を3冊以上“同時進行”
ありがちな失敗
-
SNSで評判の教材を追加購入 → 毎回違う本を開いて情報がバラバラ
なぜムダか
-
周回回数が分散し、どの教材も中途半端で終了
-
レイアウトや用語が微妙に異なり認知コストが増大
合格者の代替案
-
基礎テキスト1冊+過去問集1冊で3周
-
どうしても不安なら「弱点ピンポイント問題集」を 3周完了後 に1冊追加
-
“1冊を使い倒す” ほうが短期記憶→長期記憶の移行がスムーズ
1 位 “完璧主義”で理論が終わるまで他科目に触れない
ありがちな失敗
-
理論満点を目指して3か月→時間切れで電力・機械が手つかず
なぜムダか(最大級)
-
電験三種は 総合点ではなく科目 60 点ライン
-
理論 95 点でも機械 59 点で不合格=過剰投資が無意味
-
理論と電力・機械はリンクしており、科目横断学習のほうが理解が加速
合格者の代替案
-
理論が “試験で6割取れそう” になったら 電力へ即スイッチ
-
3科目を タテ(科目)→ヨコ(分野) にサイクル回し、飽き防止+相乗効果
-
機械は「変圧器+誘導電動機」を先に抑え、合格ライン確保後に深掘り
まとめ|“やらない勇気”が合格率を最短で高める
-
電験三種の合格ラインは 60 点 ×4 科目。
→ “上限 60 点のゲーム” では過剰投資とタイムロスが最大の敵。 -
本記事のワースト5を 自分の学習計画から削除 し、
-
直近 10 年の過去問3周
-
公式は問題で覚える
-
教材は最小限を周回
-
科目横断で早期に6割確保
-
-
これだけで 勉強時間を 20~30 %圧縮 しながら合格ラインに到達できます。
「何をやるか」より「何をやらないか」――今日そのリストを作れば、合格は一気に近づく。