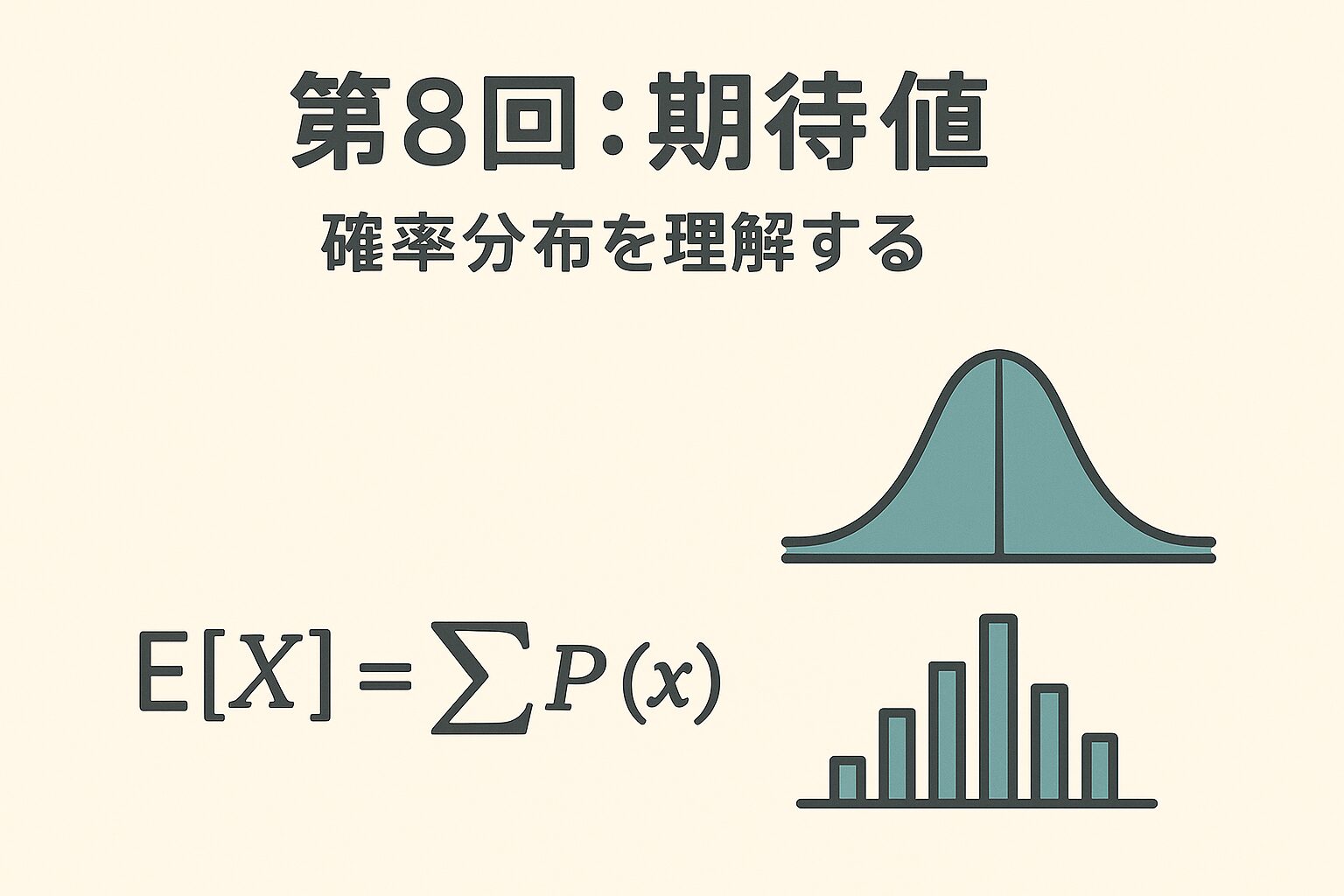こんにちは、シラスです。
「宝くじは買うべきか?」「保険には入るべきか?」「このプロジェクトに投資すべきか?」
私たちは日々、結果がわからない選択を迫られます。
そんな時、感情や勘ではなく、数学的な根拠を与えてくれるのが「期待値(きたいち)」です。
「それを繰り返した時に、平均していくら貰えるか?」
確率の重みを考慮した「予想される平均スコア」のことです。
1. 期待値の計算方法(基本)
計算はとても単純です。
「結果の値 × その確率」をすべて計算して、最後に足し合わせるだけです。
例:シンプルなルーレットゲーム
- 🔴 赤(確率 1/2):賞金 200円
- 🔵 青(確率 1/3):賞金 150円
- 🟡 黄(確率 1/6):賞金 600円
計算式:
(200 × 1/2) + (150 × 1/3) + (600 × 1/6)
= 100 + 50 + 100
= 250円
解釈 このゲームの参加費が200円なら「やるべき(得する)」、300円なら「やめるべき(損する)」と判断できます。
2. 残酷な真実:宝くじの期待値
では、みんな大好きな「宝くじ」を計算してみましょう。
(※計算を簡単にするための概算モデルです)
| 等級 | 当選金額 | 確率(イメージ) | 期待値への寄与 |
|---|---|---|---|
| 1等 | 6億円 | 約 1/600万 | 約 98円 |
| 2等〜5等 | 各種 | - | 約 58円 |
| ハズレ | 0円 | ほぼ全て | 0円 |
| 合計期待値 | 約 156円 | ||
1枚300円の宝くじを買った瞬間、その価値は数学的に「約150円」になります。
残りの150円は「夢を見る手数料(と運営費)」です。投資としては絶対に割に合いません。
3. ビジネスでの活用:投資判断
期待値が本当に輝くのはビジネスの現場です。
例えば、2つの投資プランで迷っているとします。
- 好況 (30%):+8%利益
- 普通 (50%):+5%利益
- 不況 (20%):+2%利益
- 大成功 (10%):+30%利益
- 成功 (40%):+10%利益
- 失敗 (50%):マイナス損失
一見、プランBの「+30%」は魅力的ですが、期待値を計算するとプランAの方が優秀(5.3% vs 1.5%)だと分かります。
このように、期待値は「ハイリスク・ハイリターン」の誘惑に惑わされず、冷静な判断を下す基準になります。
4. 便利な性質「線形性」
少し専門的になりますが、期待値には最強の性質があります。
「和の期待値は、期待値の和」というルールです。
E(X + Y) = E(X) + E(Y)
「サイコロ2個の合計の平均」を知りたければ、「サイコロ1個の平均(3.5)」を2回足せばいいだけ(3.5 + 3.5 = 7)。
わざわざ全ての組み合わせを表にする必要はありません。これ、計算を短縮する時にめちゃくちゃ使います。
まとめ
例えば、期待値がプラスでも「失敗したら会社が倒産する(-100億円)」ようなギャンブルは避けるべきです。
この「期待値だけで判断してはいけないリスク」を扱うのが、次回学ぶ「分散(ぶんさん)」です。
次は、複数のリスクを組み合わせた時にどうなるか?
「卵を一つのカゴに盛るな(分散投資)」の数学的意味を解説します!